リオンについて
アナログからデジタルへの大転換期にフォーカス
2022.08.25

デジタル補聴器を世界で初めて発売
リオンが日本初となる量産型の補聴器を世に送り出したのは1948年。それ以来、リオンは日本の補聴器の歴史とともに歩み、さまざまな製品を開発してきた。その中で技術的に一つの大きな転機となったのが、1980年代終わりごろから進められた補聴器のデジタル化だ。
当時、世の中のさまざまなものがアナログからデジタルへと移行する中、アメリカの大学でデジタル補聴器のプロトタイプが製作されるなど補聴器にもデジタル化の波が押し寄せつつあった。そのような状況の中、リオンではポケット型デジタル補聴器「HD-10」を世界で初めて発売する。1991年9月のことだ。
「アナログではできない音処理をしないとデジタルにする意味がないと考えていた」─ リオンの舘野誠はそう回想する。当時、アナログ補聴器はポケット型よりも耳かけ型の方が多く販売されていた。しかし小さくなるほど電圧や電力の面で設計や製作が難しくなる。「デジタルならではの機能を備えた補聴器を実現できるのであれば、たとえ耳かけ型ではなくても出す意味がある」と舘野たちは考えた。
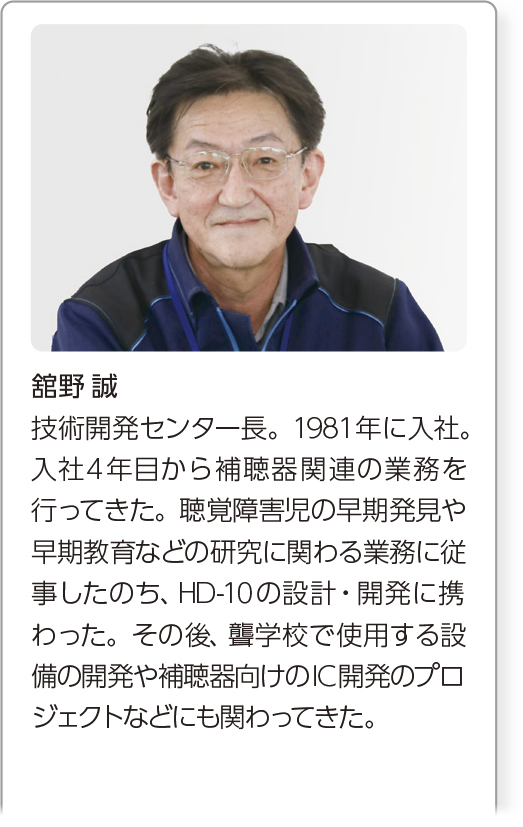
もちろん世界初の試みがすんなりと運ぶはずがない。HD-10 の開発は試行錯誤の末に実現したものだ。
デジタル補聴器では、マイクロホンに入力された音はAD(アナログ・デジタル)変換器でデジタル信号に変換され、その信号をDSPで処理したのちに再びアナログ変換して音として出力する。HD-10 の開発にあたっては、IC(集積回路)やDSP、AD変換器の調達が大変だった
と舘野は言う。「予算の関係もあり本格的なICを開発することはできません。そこで『スタンダードセル』というイージーオーダー的なICのうち、補聴器に使えそうで予算内に収まるものを探しました」
とくに苦労したのがAD変換器の選定だったと舘野は続ける。補聴器の場合、音の大きさや音源の距離などさまざまな状況にうまく対応する必要がある。さまざまなAD変換器での試行錯誤が繰り返された。
最終的にHD-10 で採用したスタンダードセルには、内部にAD変換器の回路も入っており、それが補聴器にも使える性能を持っていた。そのICが見つかったことが非常に大きかったと舘野は振り返る。

【HD-10】(1991年)
1991年に世界で初めて発売されたデジタル補聴器。入力された音を低音域、中音域、高音域に3分割してデジタル変換し、周波数帯域ごとに信号処理するため、従来のアナログ補聴器と比べて自由な入出力特性を実現した。また音の設定をいくつか保存しておいて、場面に応じてボタン一つで切り替えることができた。

【HI-P1K】(1997年)
HD-10の発売以降は補聴器専用のDSP調達に苦心しながら、デジタル補聴器の開発が進行していった。この「HI-P1K」はオーダーメイドタイプのプログラマブルデジタル補聴器として1997年に登場。音処理はアナログ回路で行われていたが、場面に応じた音の切り替えはデジ
タルで行っていたモデル。アナログからデジタルへの移行期において異彩を放つモデルだ。

【HD-11】(1997年)
1997年に発売された、他モデルとは一線を画すデジタル補聴器。低音域に対してのみ聴力が残存する最重度難聴者を対象とし、高音を聞きやすい周波数に変換する周波数圧縮型のデジタル補聴器であった。その後、耳かけ型や耳あな型でも高度・重度難聴向けのデジタル補聴器が開発されるようになり、HI-G7タイプ、リオネットピクシー、HB-W1タイプなどを発売した。
耳かけ型・耳あな型のデジタル補聴器へ
HD-10の発売後、舘野たちは耳かけ型のデジタル補聴器を開発したいという考えを抱いていた。ただ、ポケット型より小さな耳かけ型では回路の小型化が必要となり、また電池が小さくなることから使用できる電力も少なくなる。耳かけ型の実現には専用のDSPが不可欠だった。しかし「当時の日本の半導体メーカーは量産性の高いものが中心で、補聴器向けの少量生産でのIC開発は難しかった」と舘野は語る。
そのような状況の中、補聴器専用のDSPを米国ベンチャー企業から供給を受けられることになった。それを受けて耳かけ型・耳あな型のデジタル補聴器の開発を進め、1999年に「HB-D1」「HI-D1/HI-D2」が発売された。HD-10から8年を経て実現した耳かけ型・耳あな型のデジタル化だったが、まだ進化の余地は残されていた。当時の補聴器向けのDSPは、自分たちで自由にプログラミングできるわけではなかった。組み込み済みの複数の音処理のプログラムを必要に応じて選んで使うことしかできず、細かい調整はできなかったのだ。

【HB-D1】(1999年)
1999年に発売した耳かけ型のデジタル補聴器。米国ベンチャー企業のソニックイノベーション社が開発した補聴器専用のDSPの供給を受けて作られた補聴器だ。HB-D1は使いやすさ、表示などの親切さ、デザインの総合的な完成度がすぐれていることが評価され、2000年度グッドデザイン賞を受賞した。
「自分たちの思い通りにプログラミングしたい」─それが実現したのが、2009年に発売されたリオネットロゼシリーズだった。補聴器に搭載できるほど小型かつ省電力で、プログラミングの自由度が高いDSP が入手可能となったことで実現したものだ。「プログラミングの自由度が上がり、製品を改良しやすくなりました。お客様の要望に応えて満足度の高い補聴器を作りやすくなったのです」
リオンではその後、リオネットロゼシリーズを核として製品のラインアップを広げていき、2017年にはリオネットシリーズが発売された。アナログからデジタルへの転換、そしてその後の進化は「補聴器を聞きやすくできる手段があれば何でも取り入れたい」という補聴器の開発者たちの思いにより実現してきたのだ。

リオネットロゼ(2009年)
2009年に発売したデジタル補聴器。自社で自由にプログラミングすることが可能なオープンプラットフォームDSPを利用して開発した。補聴器で音のコントラストを調整し、自動的に聞きとりやすい音にする独自の技術「SSS(サウンド・スペクトル・シェイピング)機能」を搭載した。
DSPとは?
「Digital Signal Processor」の頭文字を取ったもので、AD変換器でデジタルに変換された音のデータ(デジタル信号)をもとに計算して音処理を行う装置。コンピューターでいえばCPUに当たる部分だ。たとえば大きな音と小さな音で増幅幅を変える、ノイズを低減する、補聴器で起きやすいハウリングを抑制するなどの音処理をすることができる。
取材・文/岡本 典明
- 本記事は「RION Technical Journal Vol.5」から抜粋しています。
「RION Technical Journal」は、リオン株式会社が発行する技術情報誌です。 私たちの原動力は人を助け、社会を支えたいという熱い想い。そのような情熱と創意工夫による蓄積した技術を丁寧に、わかりやすくご紹介します。是非ご覧ください。
ダウンロードはこちら
留意事項
・ご利用に関しては「利用規約」および「画像及びイラスト利用にあたっての注意事項」の内容をご確認ください。


